こんにちは、nomadbizを運営している服部です。「場所に縛られない働き方」をテーマに、スモールビジネスや地方移住、AIを活用した効率的な働き方について発信しています。
「ブログを継続できない」「文章を書くのが苦手」——そんな悩みを持つ人は多いのではないでしょうか?実は、私も以前は同じでした。しかし、AIを導入したことで執筆のハードルが大きく下がり、ブログ更新のペースが一気に加速しました。本記事では、実際に私がどのようにAIを活用し、ブログ執筆を効率化したのかを具体的にご紹介します。
まずは[前編]として、記事の構成やリサーチをAIに任せることで執筆時間を大幅に短縮できた方法と、AIと人間それぞれの得意分野を活かした効率的な執筆方法をお伝えします。

なぜ私はブログを続けられなかったのか?
書くことは決まっているのに、いざ書き始めると手が止まる
これまで私は、いくつかのブログを立ち上げては続かずに閉鎖する、という失敗を繰り返してきました。ガーデニングやDIY、家庭菜園など田舎暮らしにまつわる話題を紹介するブログ、本業のウェブ制作に関する技術的なブログ、そして今まさに書いているような「働き方」に関するブログなど、明確なテーマを持つものばかりでした。しかし、いざ書き始めると最初の1記事を書くだけでも一苦労で、全く継続できませんでした。
記事の構成を考えるのに時間がかかる
「記事にしたいテーマはあるのに、書き始めると手が止まる」「最初の1記事を書くだけで力尽きる」というのは、私にとって何度も繰り返してきたパターンでした。
書くべきことは頭の中にあるのに、いざ文章にしようとすると、何から書けばいいのか分からない。 構成を考えているうちに迷子になり、気づけば数時間が経過。そして「今日はもういいか」となり、そのまま更新が途絶えてしまう。こうした流れで、ブログが続かないまま放置されることが何度もありました。
文章のリズムや言い回しに迷い、なかなか進まない
また、文章のリズムや言い回しなど、文章表現の面でも課題がありました。気分が乗ってくると同じ表現を繰り返してしまったり、無理に凝った言い回しを使おうとして分かりにくくなったり。そうした文章の推敲に時間をかけすぎて、本質的な内容がおろそかになることも多かったのです。
なんとか書き上げても、「この内容で本当に伝わるのか?」「読者にとって有益だろうか?」と不安になり、公開をためらってしまうこともありました。何度も読み返しては微調整を繰り返し、そのうち他の仕事が忙しくなって後回しに。そして、気がつけば下書きのまま放置された記事がどんどん溜まっていく…という状況でした。
こうした課題を抱え、「もっと楽に書ける方法はないか?」と模索していました。そんな中で試してみたのが、AIの活用でした。
AIを取り入れたら、執筆のハードルが一気に下がった
最初は半信半疑だったが、試しにAIを使ってみたら…
私はウェブ制作という仕事柄、新しい技術の情報をキャッチしやすい環境にいます。AIについては以前から関心を持っていましたが、「仕事での実践的な活用」までは想像できず、正直あまり使っていませんでした。しかし、思い切ってChat GPTに「新しい事業のアイデアを提案してほしい」と相談してみたところ、私の経歴や事業内容を踏まえて「電子書籍の執筆はどうか」という具体的な提案がありました。その提案内容の的確さに驚き、AIを上手く活用すれば大きな可能性が広がるのではないかと気づかされました。
記事の構成案を考えるのにAIを活用
そして電子書籍の構想を練る中で、「並行してブログも書いてみよう」というアイデアが浮かびました。書籍の内容に沿った記事を書くだけでなく、執筆過程や構成づくりの裏側も公開すれば、同じように電子書籍を作りたい人の参考になるのではないかと考えたのです。そこで、このブログの構成を考えるところからAIを全面的に活用してみることにしました。
どのようなプロンプトで構成を作成したのか?
具体的な進め方をご紹介します。AIを活用する際に最も重要なのが「プロンプト」(指示文)です。ChatGPTでは対話形式で進めていくため、チャットにどのような指示を書くかでアウトプットが大きく変わってきます。
一例として「本とブログの連携方法を考えてください」と入力したところ、以下のような提案が返ってきました。
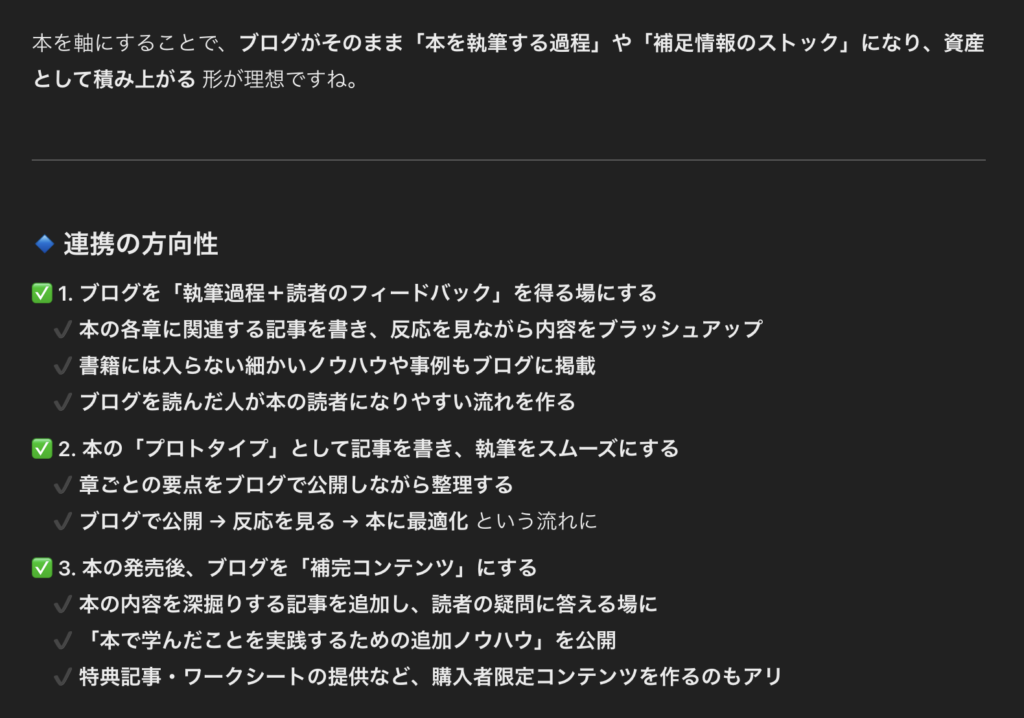
このように、わずか数秒で緻密なアイデアを提示してくれます。ただし、ここで重要なのは、これをそのまま使うのではなく、あくまで自分の考えを主軸として、AIは補助的な役割だと意識することです。AIの提案をそのまま記事にするのは簡単ですが、そうするとオリジナリティが失われ、誰にでも書けるような文章になってしまいます。それでは価値が見出せません。
AIの提案をどのように取捨選択したのか?
AIの提案を見て、コンテンツとしては十分に成立すると感じましたが、どこか「ありがち」で特別な面白さに欠けていました。また、この提案は「すでに本が完成している」という前提に基づいていたため、「これから本を書く」段階の私には、そのまま活用できない部分が多くありました。
これはプロンプトがざっくりし過ぎていて具体性に欠けていたことが原因でした。そこで、まず前提条件を整理し、全体のコンセプトを洗い出すことから始め、そのうえでChat GPTに私の考えやデータを段階的に伝えていくことにしました。
とはいえ、特に難しいことはありません。AIをアシスタントだと考えて、普段の会話のように対話を重ねていきました。例えば「この提案は本が完成してからでないと使えません。私は本とブログを並行して書いているので、そのリアルタイム感を活かせるような案はありませんか?」といった具合に質問すると、それに沿った提案が返ってきます。このようなやり取りを繰り返すうちに、AIの回答がより的確になり、私の目指す方向性に合った提案へと進化していきました。
具体的には以下のようなイメージです。
最初のプロンプト
「本とブログの連携方法を考えてください」
AIの回答:
- 本の内容を要約してブログ記事にする
- 本の一部を無料公開する
- 読者向けに補足コンテンツを作成する(→ ありがちすぎる)
改善後のプロンプト
「私は本とブログを並行して書いています。執筆の過程を読者と共有しつつ、リアルタイムでブログを活用できる方法を提案してください。」
AIの回答:
- 「本の目次をブログで公開し、読者の関心が高い章から書き進める」
- 「記事の最後に『この記事の作成にAIをどう活用したか』を記載し、AIの実践例を蓄積する」
- 「本の執筆進捗をリアルタイムで共有し、読者と対話しながら方向性を調整する」(→ 実際の目的に合った提案になった!)
これらのやり取りを通じて、提案内容がより具体的になり、記事の構成や展開の順序が明確になってきました。さらに、やり取りを重ねる中で「このAIとの対話プロセス自体が有益なコンテンツになる」というひらめきを得て、これも記事に織り込むことにしました。
AIと人間の役割分担——どこまでAIに任せる?
AIとの対話を繰り返す中で、AIの得意分野と不得意分野が徐々に明確になってきました。それぞれの特徴を具体的に見ていきましょう。
AIが得意な部分:記事の構成・リサーチ・校正
AIに記事の構成を提案してもらうことで、執筆スピードが格段に上がる
まず、記事の骨組みを作成し構造を整理する点において、AIは非常に論理的な提案をしてくれます。そのまま使えない場合もありますが、全体の構成を俯瞰できるため、「この内容で書けそうか」「この記事は面白いか」という判断が素早くできます。そして「よし、書こう」と決めたら、すぐに執筆に取り掛かれるのです。
例えば、「地方移住すると生活コストは本当に下がるのか?」 という記事を書こうとした際、AIに「このテーマで記事の構成を考えてください」とプロンプトを入力しました。
すると、以下のような提案が返ってきました。
- 地方移住の生活コストに関する一般的なイメージ
- 実際のデータ:都会と地方の生活費の比較
- 本当に安くなるのはどの部分?
- 逆に地方移住でコストが増える部分
- 総合的に見て、移住はコストダウンにつながるのか?
- 私自身の経験談と結論
これをベースに、「この見出しはもう少し具体的にしたほうがいい」「ここは自分の体験談を入れよう」 という形で調整していくと、あっという間に記事の骨組みが完成しました。
私の場合、この「骨組みを作る」作業が苦手で、先に細部から詰めていってしまう癖がありました。そのため、なかなか執筆に取りかかれないことが多かったのですが、AIを活用し始めてからは、記事の構成を非常にスムーズに整理できるようになりました。
記事のリサーチをAIに頼ることで、下調べの時間を短縮できる
また、記事を書く上で欠かせないリサーチに関しても大いに活用しています。例えば上と同じ「地方の生活コスト」について記事を書くときに、自分の体験談だけでなく、客観的なデータを提示した方が良い場合があります。そういったときに、以下のようにAIを活用します。
- プロンプト:
「地方移住の生活コストについて、都道府県別の平均家賃、食費、光熱費のデータを調べてください。」 - AIの回答:
- 総務省の統計データを元に、都道府県ごとの生活費の比較情報を提供
- 家賃の全国平均を提示し、地方と都市部の差をざっくりと把握
- 「地方移住で意外にかかるコスト」の項目(例:車の維持費、暖房費など)を提案
AIリサーチの活用ポイント
- わざわざ総務省のサイトや統計データを探しに行かなくても、大枠の情報を数秒で得られる
- さらに深堀りが必要な部分だけを自分で調べればよいので、リサーチの時間を大幅に削減
このように、AIを活用することで、下調べにかかる時間を削減し、執筆により多くの時間を割けるようになりました。
校正や言い回しの調整をAIに任せることで、文章の質を向上させる
はじめにも少し触れたように、文章のリズムや言い回しに悩んでいたことが、ブログを続けられなかった大きな理由でした。しかし、AIを活用することでこの問題が大幅に改善されました。
私はこれまで5冊の書籍の出版に関わってきましたが、執筆過程で大きな時間を使ったのが「校正」と「推敲」です。誤字脱字や文法ミスを正し、文章の流れを整える作業は、正確な情報を伝える上で不可欠ですが、集中力を要するため、負担の大きい作業でした。
現在はこの作業に、ChatGPTではなく主に「Notion AI」 を活用しています。Chat GPTは内容を勝手に書き換えたり加筆をすることがあり、それがどうも自分らしさを損なう気がしていました。その点Notion AIはシンプルで、文章を選択して指示を出すだけで、すぐに校正・推敲を行ってくれるため、作業スピードが大幅に向上しました。提案された修正をそのまま採用するわけではありませんが、多くの場合「より分かりやすくなった」と実感しています。ただし、AIに頼りすぎると「自分らしい文章」が失われるリスクもあるため、最終調整は必ず自分で行うようにしています。
人間がやるべき部分:体験談・独自の視点
AIにはできない「体験談」こそが価値になる
AIは膨大な情報をもとに的確な提案をしてくれますが、「自分が実際に経験したこと」までは語ることができません。 つまり、一次情報や個人的な体験談は、AIには絶対に作り出せない領域です。
このブログや執筆中の書籍では、すべて私自身の体験を土台にし、掲載している情報も一般的なもの以外は、実際の私のデータに基づいています。 「地方移住の生活コスト」についても、統計データだけでなく、実際に私が払っている金額や、移住後に感じた意外な出費などを交えながら紹介しています。
AIの活用によって記事の構成や推敲を効率化できたのは事実ですが、最も価値があるのは、私自身のリアルな経験です。 AIが量産する一般論ではなく、読者が「ここでしか読めない情報」と感じてもらえるような内容を届けることを強く意識しています。
AIの提案をそのまま使わず、自分の言葉に落とし込むことが重要
これを実現するために、「AIの提案をそのまま使わない」という姿勢がとても重要です。AIが生成する文章は論理的で分かりやすく、時には自分で書くよりも優れていると感じることがあります。そのため、「このままコピペで使えるのでは?」という誘惑に駆られがちです。
しかし、人の話し方や声色に個性があるように、文章にもその人らしい表現や雰囲気があるものです。特に体験談では、そのときに感じたことや思いを「自分の言葉」で伝えることで、臨場感が生まれ、読者にとってより興味深い内容になります。
文章の上手さは、必ずしも「面白さ」と直結しません。むしろ、完璧に整いすぎた文章では、かえって感情の機微が伝わりにくくなることもあります。AIを活用する際は、単に「美しい文章」を目指すのではなく、「自分らしさをどう表現するか」を意識することが大切です。
独自の視点を組み合わせることでオリジナリティの高い内容に
「自分らしさ」を表現するための重要な要素は「独自の視点」です。例えば「地方移住」について書かれたブログや本は数多くあります。「ウェブ制作」や「AI活用」についても同様です。
しかし、「ウェブ制作者が田舎暮らしをしている」「AIを活用してスモールビジネスを展開」といった視点を組み合わせると、ぐっとオリジナリティが増します。さらに、「ウェブ制作を軸としたスモールビジネスをAIで効率化し、その結果、住む場所が自由になって地方移住を実現した」といういくつかの要素を掛け合わせると、より独自性の高い内容になります。さらに私には「ラッパーをしていた」「バリ島でウェブ制作を始めた」という、少し珍しい経歴もあり、これらを組み合わせることで可能性は無限に広がります。
もちろん、似たような経験をしている人もいるでしょうから、「私だけの視点」と言い切れるわけではありませんが、少なくともAIには導き出せない、リアルな経験に基づく視点があるはずです。
後編ではさらに具体的な実践例をご紹介
AIの活用で、ブログ執筆の効率は劇的に向上しました。しかし、最も重要なのは「自分にしか書けない体験や視点」です。[後編]では、さらに具体的なAI活用術と、それを活かした実践例をご紹介していきます。
一つ確実に言えるのは、AIは私たちの「創造性」を奪うものではなく、むしろ引き出してくれるツールだということ。AIと上手に付き合いながら、より価値のある情報発信を目指していきましょう。
(後編に続く)




コメント